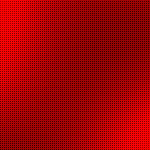製品を作る際に多くの材料や部材、部品を用いているケースでは原産材料なのか、非原産材料なのか全くわからないものが混ざることもあります。どちらかわからないもので、裏付けのとれない、もしくは取りようのないものについては「非原産材料」としてカウントすることになります。より正確に言えば、証拠書類(エビデンス)がそろっていないものは、たとえ目の前で製造しているところを証明できたとしても、非原産材料にするしかありません。
というのも、FTAやEPAにおいて関税の優遇を受けることが出来る条件の一つとなっている原産材料とは「特定原産品」のことであり、協定を締結している国同士のいずれかの原産品であることが「書類で確認できるもの」のことです。
書類は公的なものがあればそれに越したことがないですが、自社内での原産割合の計算書や、部品を購入しているメーカーから発行してもらったサプライヤー証明書などもこれらを裏付ける書類となります。こうしたものが一切なく、発行してもらうことも困難なものは、非原産材料としてカウントします。
これは原産品であることを証明する原産地規則のうち、関税分類番号変更基準であっても、付加価値基準であっても同じです。